
2011年1月のドーハ(カタール)滞在は、落ち着いた、とても楽しい時間だった。
1月7日に開幕し、29日に決勝戦を迎えたアジアカップ。ザッケローニ監督率いる日本代表が見事なサッカーで優勝を飾ったこともある。だがそれ以上に、1月のドーハの快適な気候が、穏やかで平和な雰囲気をかもし出していたからだ。
このカタールで行われる2022年ワールドカップの開催時期について、議論がやかましくなっている。今週の木曜日と金曜日に開かれる理事会で、国際サッカー連盟(FIFA)はこのテーマを検討する予定だ。
ワールドカップは6月~7月開催が原則。過去19回のワールドカップは、5月末開幕が3回あったものの、例外なく6、7月中に開催されてきた。
ところがこの時期のカタールは平均最高気温が40度を超し、日によっては50度にもなるという酷暑の季節。こんなことは開催決定時(2010年12月)に明らかだったにもかかわらず、最近になって問題化しているのだ。
スタジアムやファンフェスタを地域まるごと冷房するという開催案で、カタールは支持を得た。しかし自身カタールに一票を投じた欧州サッカー連盟のプラティニ会長は、決定直後から「冬季開催」を主張してきた。そして最近、FIFAのブラッターがそれに同調する考えを表明した。
気候の面では22年1月が理想だが、冬季五輪と重なってしまう。現状では同年の11月から12月という案を支持する人が多い。
だが反発もある。最も過激なのはイングランドだ。シーズンの最盛期に2カ月近くも日程を空けなければならないのは、前後3シーズンにわたって放映権料やスポンサー契約などで大幅な減収になるというのだ。ただ他の欧州主要国に「共闘」を求めたところ、ドイツを始めとした欧州諸国は「選手に負担のかからない冬季がいい」という意見が強く、現状では孤立状態だ。
FIFAの理事たちがカタールに票を入れた経緯はともかく、犯罪がほとんどなく安全なカタールでのワールドカップを私は楽しみにしている。世界の人びとがカタールのような穏やかなイスラム国を経験することは、21世紀の世界に大きなプラスになるはずだ。
だが開催時期はもちろん冬だ。6~7月ではない。ワールドカップはスタジアムやファンフェスタだけではなく、その国での滞在自体を楽しむもの。昼間出歩くことができない大会などありえない。

カリファスタジアム
(2013年10月2日)
なんとも奇妙な「改革」ではある。15年からのJリーグ年間チャンピオン決定方式だ。
1回戦総当たりを2ステージ(2回優勝が決まる)行い、その後に年間チャンピオンを決めるポストシーズントーナメントを計4試合行う。
奇妙なのは、全国のサポーターたちが「不公平なシステム」と反発するなかで、Jリーグも「ホーム&アウェイで対戦して、年間成績で一番を決めるのがスポーツ上公平」(中西大介Jリーグ競技・事業本部長)と新方式が理想でないことを認めていることだ。
以前、2ステージ制が04年まで11シーズンにわたって実施された。そのうち実に7シーズンで、実際には年間成績がトップだったチームが優勝を逃している。99年には「年間6位のチャンピオン」まで生まれている。
ではなぜJリーグは敢えて再び「不公平」を演出しようとしているのか。その背景には、深刻な財政難がある。欧州サッカーに圧倒されて観客数や関心が伸び悩んでいるだけでなく、スポンサー収入が減り、クラブへの配分もJリーグ自体の事業にも支障をきたしかねない事態を迎える恐れがあるという。
何より懸念されているのが選手育成にかける事業の継続が危ぶまれていることだ。Jリーグはクラブが行っている育成活動を支援し、同時に、13歳以下から1歳きざみのリーグ戦も主催している。未来への投資を減らすことは、自らの未来を閉ざすこと。育成事業は何としても継続しなければならない。
その資金を確保することが、今回の2ステージ制復活の大きな目的だ。終盤戦のテレビ中継が、近年はほとんど行われていない地上波での放送を含め、高額で販売できそうなのだ。優勝争いが地上波で放映されることで一般の関心も高まり、人気再上昇のきっかけにもなるのではと、Jリーグは期待している。
ただし今回の改革が「緊急避難」的なものであることは誰にもわかる。収入を確保し、関心が高まったとしても、それは一時的なものにすぎない。危機から脱するには、Jリーグをより魅力あるものにするしかない。
観戦環境の整備、試合運営の改善、魅力ある選手の育成など、あらゆる面での努力が必要だが、何より重要なのは、選手たち自身が危機感を共有し、魅力あふれる試合をつくり出していくことだ。
選手こそJリーグの「主役」であり、選手たちがつくり出す試合こそ、Jリーグ唯一の「商品」なのだから。
(2013年9月25日)
9月か10月にかけて日本サッカー協会が初めての大がかりな調査を実施する。「サッカーファミリー・カウント2013」。21世紀の日本のサッカー界に大きな影響を与えそうな重要な調査だ。
日本協会の登録選手数は今世紀にはいって微増しながら現在約百万人。Jリーグ以前より4割近く増えている。少子化が進む日本では希有な「成長部門」と言っていい。
だが最近の調査で驚くべきことが判明した。登録選手が毎年2割、すなわち20万人も入れ替わっているのだ。さらに言うと、高校を卒業する年代の選手が登録を継続するのは2割に過ぎず、実に8割の選手が「消えて」いっているという。
そもそも選手登録制度とは「公式大会」を公平に実施するためのもの。大会のためだけに他チームから補強するなどの不正を防ぐことを目的としている。公式大会出場を目指さなくなった選手、あるいは不参加を前提としているチームには、登録費を払うメリットはほとんどない。
Jリーグ誕生のはるか前から、日本のサッカーには「二重構造」が存在していた。
日本サッカー協会は日本のサッカーを統括する唯一の組織。各種の全日本選手権を頂点とした公式大会を主催し運営している。そして傘下の47都道府県協会が、その仕事を分担している。
その一方、全国の市区町村が所有するサッカー場を住民のために運用する組織として、各地の教育委員会の下などに置かれた「市区町村のサッカー協会」が存在する。基本的に日本協会とは無関係の組織。日本協会への選手登録をしなくても、市区町村の協会主催の大会でサッカーを楽しむことが可能なのだ。
今回の「カウント」は、実態把握が難しいフットサル(5人制サッカー)の競技人口、低学年が登録されていない小学生年代の実態調査とともに、市区町村の協会の枠内で活動しているチームの選手数を把握することを主目的としている。
「競技会を目指さなくなっても、引き続きサッカーを楽しんでいる人がたくさんいる。そうした人びとがただ『登録を外れる』のではなく、サッカー界に何らかの『籍』を残す仕組みを考え、サッカーを楽しむ機会をより多様にして、生涯スポーツとしてのサッカーを振興することに今回の調査を生かしたい」(日本サッカー協会)
それは日本のサッカーが成熟に向かう重要なステップになるだろう。実りある調査になることを期待したい。

(2013年9月18日)
たくさんのトルコの人びとが、フェイスブックに「おめでとう東京」のメッセージを書き込んでいるという。
2020年夏季オリンピック東京開催。競技場や練習場などスポーツ施設だけでなく、各種インフラの整備が進み、21世紀の東京ひいては日本のスポーツと生活の基盤がつくられることだろう。
もちろん、どの競技も競技力を上げ、金メダルを増やしてほしい。だがそれ以上に願うのは、この大会で世界に何かを提示したいということだ。
1964年の東京五輪は、日本国民にスポーツの素晴らしさと自ら参加することの喜びを教えた。56年後の2回目の五輪では、競技者・役員だけでなく観客も国民も成熟したスポーツ文化を共有し、世界に示すことができたらいいと思うのだ。
いまの日本では、勝てば大喜びする一方、負ければ仏頂面でうなだれるという「型」がある。勝つために全力を尽くすのはスポーツで最も重要な基本的態度だが、勝つことはすべてではない。
競技が終了すれば勝者も敗者もない。ともにスポーツを楽しんだ仲間がいるだけだ。仲間であれば、勝った者が相手を気遣って態度を慎み、負けた者も悪びれずに相手を称えるだろう。
元来、日本のスポーツにはこうした態度があった。根底に武道の精神が流れていたからだ。「勝っておごらず負けて悔やまず、常に節度ある態度を堅持する」(日本武道協議会『武道憲章第3条』)という「残心(ざんしん)」の教えが生きていたからだ。
だがいつのころからか、あたりかまわず狂喜する勝者と、大げさに倒れ伏したりふてくされてしまう敗者ばかりになってしまった。敗者はうなだれ、「恥じている」ことを示さなければ済まない空気になってしまった。
Jリーグでは、勝ったチームがサポーターに向かって手を振る一方で、負けたチームは「すみませんでした」とばかりに深々と頭を下げる。力の限りに戦った結果なら、負けても胸を張って手を振ればいいではないか。
7年後にオリンピックを迎えるときには、世界に誇ることのできるスポーツ文化の国でありたい。勝っても負けても、試合後には互いに笑顔で称え合う選手たち、そして観客・国民でありたい。
東京に祝福の言葉を贈るトルコの人びとの話を聞いて、「オリンピックのホスト国にふさわしいのは、トルコのほうだった」と感じたのは、私ひとりではないはずだ。
(2013年9月11日)
9月になったばかりだが、私の胸には、「ことしいちばん印象に残ったゴール」がすでに決まっている。
6月4日、ワールドカップ出場をかけたオーストラリア戦。終了直前に本田圭佑が決めたPKだ。左足から放たれた弾丸シュートがゴールネットの中央を大きくふくらませ、一瞬止まった光景は、本当に感動的だった。
埼玉スタジアムのゴールネットが大きくふくらんだのは、六角形に編まれたものだったからだ。その六角編みのネットを日本で開発したのが、福井ファイバーテック株式会社(愛知県豊橋市)代表取締役社長の福井英輔さん(58)だ。
慶応大学でFWとして活躍、強化に力を入れていたヤマハ(現在のジュビロ磐田)に選手として入社したサッカーマン。89年に実家に戻り、家業の漁網会社の仕事に取り組み始めていたときに、90年ワールドカップ・イタリア大会を見た。
ゴールが決まると、ボールの勢いでネットが大きくふくらみ、感動が増した。さすがは専門家、ネットが「六角編み」であることに気づいた。当時日本ではすべて「四角編み」。シュートが強いとポンとはね返ってきた。六角編みには日本に数台しかない特殊な編み機が必要なのだが、幸い会社にあった。
試行錯誤、4年間をかけてサッカーに適した六角編みのネットの開発にこぎつけた。95年に磐田のスタジアムに取り付けられたのが日本で最初の六角編みのゴールネットだった。その良さが認められ、02年ワールドカップでは日韓の全20スタジアムで採用された。
だがゴールネットはいちど購入すれば何年間も使われる。とてももうけなど出ない。いまではサッカー関係事業の担当者は、社長ひとりだという。
それでも福井さんの情熱は尽きない。Jリーグでクラブカラーに合わせたカラーネットを推進するなかで、ワールドカップでは出場32カ国の色を使ったネットで「平和の祭典」をアピールしようという活動も始めている。
だが福井さんが最も愛情を注いでいるのは94年に六角編みネットをつけて発売した軽量小型ゴールだ。
「ミニゲームでもネットのついたゴールがあったほうがいい。子どもたちにも、ぜひボールがネットに吸い込まれる感動を味わってほしい」(福井さん)
伝説の名選手・杉山隆一監督自らにスピードと決定力をほれこまれ、ヤマハに入社した福井さん。「ストライカー魂」は衰えることを知らない。
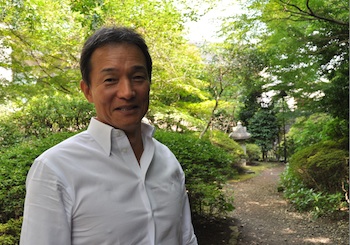
(2013年9月4日)